開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
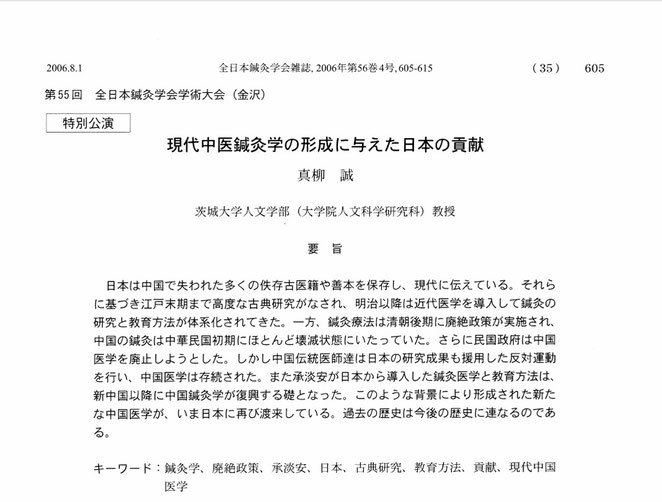
以前、日本鍼灸と中国鍼灸の関係を調べていました。中国から鍼灸が日本に伝来したのは間違いないことなのですが、日本独自の発展をしたのも確か。源流が同じでもかなり相違があります。鍼灸学生時代は興味がなかったせいでそこら辺のところがよく分かっておらず、定期試験をパスすれば、国家試験に合格すればいい、という程度の勉強だけでした。鍼灸師になって5年後、呉竹学園鍼灸マッサージ教員養成科に進学します。その時には経絡治療と中医学の違いを学ぶことになり、なるほどと思いました。そこから更に学びを深くしていくと経絡治療が(伝統と言われる)日本鍼灸そのものというわけでもなく、中医学が中国鍼灸とイコールではない、ということが段々分かってきました。というより日本鍼灸とは?中国鍼灸とは?という話で。今は鍼灸学生さんに東洋医学の事を教えることもあるので(それこそ東洋医学とは?という問題があるのですが)、より深く調べようとしていました。
そのようなときに全日本鍼灸学会学術大会の情報がヒットしました。
これは金沢で行われた全日本鍼灸学会学術大会での特別公演の内容を全日本鍼灸会雑誌(2006年第56巻4号)に掲載されたものようです。著者は茨城大学人文学部(大学院人文科学研究科)教授(※当時)真柳誠氏です。真柳誠氏は薬剤師、鍼灸師であり医学史学者であります。現在は茨城大学名誉教授となっています。余談ですが東京理科大学薬学部卒で私にとって大学の先輩でもあります。その医学史を専門とする教授が記したもの。要旨にこのような文章がありました。抜粋します。
『
(前略)
一方、鍼灸療法は清朝後期に廃絶政策が実施され、中国の鍼灸は中華民国初期にほとんど壊滅状態にいたっていた。さらに民国政府は中国医学を廃止しようとした。しかし中国伝統医師達は日本の研究成果も援用した反対運動を行い、中国医学は存続された。また承淡安が日本から導入した鍼灸医学と教育方法は、新中国以降に中国鍼灸学が復興する礎となった。このような背景により形成された新たな中国医学が、いま日本に再び渡来している。過去の歴史は今後の歴史に連なるのである。
』
何となく知識としてあったのが『鍼灸療法は清朝後期に廃絶政策が実施され、中国の鍼灸は中華民国初期にほとんど壊滅状態にいたっていた。さらに民国政府は中国医学を廃止しようとした。』という事実。詳しくは本文を読んでみましょう。「5.近代日中の鍼灸」の項を一部抜粋します。
『
中国では清の1822年(文政5年)、皇帝の体に鍼や灸をする行為は許されないという勅令により、宮廷の太医院で鍼灸科が廃止されました。そして皇帝に禁止された鍼灸治療は、むろん民間でも行ってはいけないことです。
(中略)
そして中国ではこの勅令が出た1822年から清末までの約100年間、ずっとはり灸の暗黒時代で、民国初期には殆ど壊滅状態になっていました。
』
このように中国では清時代の100年間、鍼灸が禁止されてその技術は失われそうになっていたのでした。真柳誠氏の言葉を借りれば殆ど壊滅状態。
次にまた要旨に戻ると『また承淡安が日本から導入した鍼灸医学と教育方法は、新中国以降に中国鍼灸学が復興する礎となった。』という個所。承淡安という人物が日本で鍼灸と教育方法を導入したというわけです。この承淡安という人物について「11.承淡安と近代中医鍼灸」という項で説明されています。抜粋します。
『
さらに1934年(昭和9年)から1935年(昭和10年)の8ヵ月間、承淡庵は来日して日本の先進的な鍼灸教育を調査しました。彼は東京高等鍼灸学校(呉竹学園)にて約半年ほどの授業を受け、終了時には日本の鍼灸教育を受けたという資格証を受け取ります。この時に坂本貢校長は目黒の雅叙園で特別に宴を催し、彼の終了を祝賀しました。
』
承淡安を承淡庵と表記していますが同じ人。調べてみると複数の表記法が見つかりました。何より注目したのは戦前の昭和9年(1934年)から昭和10年(1935年)にかけて8ヵ月来日して、旧東京高等鍼灸学校で半年間授業を受けていたということ。この東京高等鍼灸学校とは現在の呉竹学園東京呉竹医療専門学校のこと。私の母校なのです。またここで登場する坂本貢校長は現在の呉竹学園理事長坂本歩氏の祖父にあたる人物です。
この事実に大変驚きました。母校に中国鍼灸界の重要人物が学びに来ていたとは。承淡安がどのような功績を残したのかはまた別の機会に詳しく触れますが、とにかく近代の中国における鍼灸において多大な功績を残した人物です。その人と母校と関りがあったとは。呉竹学園は1926年に創設されていますから1934年当時はできて8年ほど。別の資料によると承淡安は中国に帰国後、多くの後進を育成し、彼が養成した直接の門人は数百名、通信教育等も含めると3千数百名になると言われています。そこには少なからず呉竹学園の教育が影響していることでしょう。このような歴史があったとは知りませんでした。
呉竹学園東京呉竹医療専門学校。私が通ったときは東京医療専門学校という名称でした。鍼灸マッサージ科、柔道整復科、鍼灸マッサージ教員養成科と3科を卒業しています。そして約90年前に東京高等鍼灸学校という名称だった頃、中国鍼灸史に名を残す承淡安が学んでいた。このことは大きな驚きでした。同時に母校の伝統とその影響を再認識させられました。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください