開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
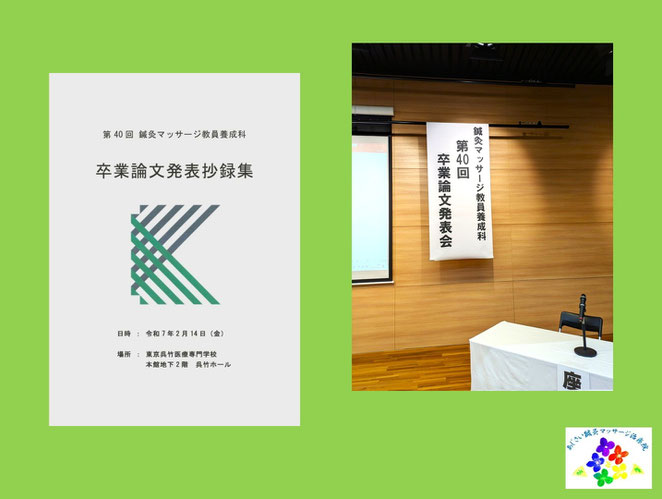
今年も母校である東京呉竹医療専門学校鍼灸マッサージ教員養成科卒業論文発表会に参加してきました。今年の発表は41期生。発表会自体は40回目の節目となります。今年は昨年竣工した新本館地下の呉竹ホールでの開催です。教員養成科の校舎は5号館なのですが発表会は本館で。広くて新しい、学会や卒業式・入学式も開催できる設備です。40回目を新しい会場で迎えました。
私は教員養成科30期。2年生が教員養成科の集大成として行うのが卒業論文発表会。抄録作成、論文提出、そしてスライドにまとめて内容の発表。学内と言えど学会発表ということで緊張します。そして1年生が会場で手伝いをしつつ公聴。2年生の研究発表を聴いて1年後の発表に備えます。この日から卒業研究が始まるのです。
今年発表する41期の2年生。知り合いの先生が3名いました。過去に業界研究を兼ねて当院に来院した方々。本校教員養成科に進学し、そして卒業。感慨深いものがあります。そして今年は昨年から教員養成科進学を考えている他校(東京呉竹医療専門学校ではない鍼灸専門学校)の2年生が会場で参加。また今年から校舎が一緒になったので鍼灸マッサージ科の学生さんも会場にいました。在校生も他校の生徒も参加できる開かれたものとなりました。とても良いことだと私は考えていて、日本で一番古くからある鍼灸マッサージ教員養成科で、全国の専門学校から生徒が集まっている本校。研究内容も素晴らしいものがあると手前味噌ながら思っているので、外部に知ってもらう方が業界にとっても学校にとっても好ましいでしょう。
今年も各演題を紹介しつつ、発表を聴いた感想などを書いていきます。発表や論文には著作権が発生するのでキモとなることは極力紹介しないで実験手法を中心に。その上で私個人の考えや補足を加えていきます。
1.不眠症状に対する鍼が睡眠の質に及ぼす影響について -睡眠とストレスの関連性-
睡眠障害に対する毫鍼(人体に刺入する鍼)による施術効果を実験で検証します。質問紙法で不眠症状がある被験者に対して「百会」、「内関」、「神門」という自律神経調整によく使われる経穴(いわゆるツボのこと)に刺鍼します。腕時計型睡眠計を着用して覚醒時間、浅い睡眠、深い睡眠、ノンレム睡眠(%)を測定。鍼刺激の前後に唾液アミラーゼモニターでストレスレベルをチェック。また質問紙法(アンケート)で自覚的な症状を調査します。経穴の選定は先行研究から。内関、神門は手首にあるので刺される方は刺激が強いと言えます。器材を用いて数値測定をして客観的なデータをとります。またアンケートで自覚的な症状に対する点数も出します。
本研究テーマは昨年発表された「不眠症状に対する円皮鍼が睡眠と心拍に及ぼす影響について」の続報と言えます。このときは円皮鍼というシールに棘状の鍼がついていて貼ったまま生活ができる種類の鍼を用いました。今回は毫鍼にしています。使う経穴も一つ変えています。昨年の発表を聴いた上で違った手法で研究を行う。教員養成科らしいものです。
測定ツールが進化して自宅での就寝時にデータを計測できるようになりました。一昔前だと病院に入院して計測していたかもしれません。専門学校レベルの研究でも10年前では考えられなかったデータを取ることが可能に。また自覚的な数値と比較することで結果の相違が分かります。自覚としては凄く効いているが客観的なデータはそうではない、ということが往々にしてあります。そのことにも意味があるので考察の材料になります。
2.眼周囲温熱療法が眼の調節機能に及ぼす影響 -眼疲労や視力改善に対する治療効果の検討-
本校教員養成科の卒業研究では目に関する研究(視力、眼精疲労など)が多数報告されてきました。昨年も「目の疲労に対する鍼治療の効果」という演題で発表がありました。私の同期も目に関する研究をしました。その定番と言える目に対して、くるみ灸と蒸気アイマスクという温熱療法での刺激で実験をしています。くるみ灸というのは本当にくるみの皮の上に艾を乗せて燃やします。それを目の上に置くのです。教員養成科で習った特殊灸法であまりお目にかかることはないものです。それに対して市販している蒸気アイマスク、商品名「めぐりズム」を使用し、視力と眼疲労の自覚を計測しています。
目という繊細な器官であるため、局所に鍼を刺すという事はほぼ不可能です。そのため目の周囲、あるいは経絡を考えて経絡上の遠い経穴を選ぶこと実験がこれまでありました。間接灸に該当する目の周囲を温めるくるみ灸に目を付けたのが秀逸です。当然眼球に直接お灸をすることはできません。さらにくるみ灸ではなく簡便な市販蒸気アイマスクを用いたら効果に差があるのかを検証しているのです。臨床的なことを考えた研究内容と言えます。くるみ灸は準備、取扱いがかなり大変でなかなか鍼灸院でするのは難しいのです。それならば代用できないのかという発想。このような発想をするのが教員養成科の特徴になっていると私は考えています。
3.ストレッチングと鍼刺激による筋緊張低下効果の比較 -腹筋内側に対して筋硬度計とVASを用いた検討-
鍼を刺すことで筋肉の緊張を下げることができます。他動的にストレッチをかけることでやはり筋肉を緩めることができます。効果は同じでもその作用機序は異なると言われています。鍼と徒手。技術的にも違います。それを比較した実験研究です。利き足の腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)を対象に、筋緊張を増大させるために運動負荷を被験者に行い、24時間後に鍼刺激とストレッチをそれぞれ行い筋肉の固さを測定するのと10m歩行させて筋肉の突っ張り感を自覚的に調査します。
似たような研究として私の同期が筋肉痛を鍼刺激で予防できるのかと考え同じように腓腹筋を対象に実験したことがありました。目的は異なりますが運動負荷をかけた上で鍼刺激を行うことは同じです。私は被験者になったので既視感がありました。結果は意外なものになりました。それに対する考察が確かになと納得できるものでした。鍼とストレッチ。どちらがいいのかという問いは、臨床現場なら両方やるよね、という答えになります。患者さんにとって良いと思うことはやる、というのが自然な考えでしょう。その上で敢えてこの2つを比較する研究を聴くことで今まで考えたことがなかったものがありました。鍼刺激と手で触れる触圧刺激も加味されるストレッチ。それを並べることなど頭にありませんでした。
4.円皮鍼による刺激が母音のフォルマント周波数に与える影響
この卒業論文発表会では毎回、初めて知る用語が多々あります。今回はフォルマント周波数です。事前に抄録を読んで初めての言葉で調べました。フォルマント周波数とは発声する際の声道の共振周波数をいいます。日本語の母音を区別する要素になります。周波数の低い方から第1フォルマント周波数(F1)、第2フォルマント周波数(F2)、としていきます。鍼刺激がこのフォルマント周波数に影響を与えるのかを実験しています。ダブルブラインド(二重盲検)という手法をしています。これは円皮鍼という貼るタイプの鍼を用いているのですが、偽鍼として鍼がついていないものも使用します。それは外見では違い分かりません。円皮鍼は非常に短い長さなので被験者も鍼を刺されている実感がありません。よって本当に円皮鍼を刺されているのか鍼のついていないものなのか認識できないのです。更に実験者にも貼っている円皮鍼が本物か偽物か分からない状態で実験をします。実験者、被験者共に分からないのでダブルブラインドです。薬剤の実験では一般的に行われるダブルブラインド私見ですが、鍼灸では非常に難しいのです。それができる数少ないやり方を採用しています。経穴は「肺兪」、「中府」という肺経の兪募配穴を採用しています。発声に関わる五臓は肺で胸部、背部の両方を用いる兪募配穴という経穴の選び方。鍼灸師には非常にオーソドックスなやり方です。母音の発声をPraatという装置でF1、F2のフォルマント周波数で計測します。
声、発声を対象にした研究も教員養成科ではされてきました。私の同期も発生に対する鍼刺激で実験をしています。今回のものは円皮鍼という弱視激であるがブラインド試験ができるものを採用したこと。喉という局所ではなく鎖骨下の胸部「中府」、背中の「肺兪」という離れた部位を選択し、かつ古典の考えを採用している点が特徴です。更にフォルマント周波数という専門的な指標を用いている。肺活量や声の高さといったものではない。そしてフォルマント周波数を計測できる装置がある(研究に利用できる)。目の付け所が違うなと感じます。
5.冷え症に対する温筒灸とショウガ湯の相乗効果 -ショウガを摂取した際の三陰交の有効性について―
冷え症に対してお灸という外部刺激とショウガ湯摂取という体内に入れることの2つを用いた実験研究です。事前に冷え症がある女性10名の被験者に対して、ショウガ湯を摂取したあとに「三陰交」という経穴に温筒灸を行い、足表面温度と体温を測ります。また「冷え日記」での回答、冷えの程度をVAS(Visual Analog Scale)で計測します。温筒灸は商品名でいうと達磨灸というもので燃える艾部分と皮膚の間に空間があります。ショウガ湯は発熱作用がある生姜の粉末をお湯に溶かしたもの。日絵日記というのは14項目の質問を6段階(0~5)で採点してもらうものです。
私は会場でも発言したのですが、摂取するものと鍼灸師の本分である灸を組み合わせた実験デザインに感心しました。これまでクラフトコーラなど被験者に摂取させる研究はありましたが、それと灸刺激を合わせている。大学病院で勤務した際に医師らと話していて、東洋医学のうち特にとっつきにくいのが気の概念と経絡・経穴です。特に約400ある経穴と14個はあるメジャーな経絡を覚えるのはしんどいです。薬を処方できる医師にとっては直接体内に投与できる術を持つので、外部(体表の経穴)から(経絡を経由して)内部(臓腑など)に効かせることを考える鍼灸師のやり方は分かりづらいでしょう。また日本では漢方薬も薬剤師の範疇なので(登録販売者になればまた話は別です)一般的な鍼灸師には漢方は手が出せません。ショウガ湯という市販されているものと組み合わせて実験するという発想が臨床現場を想定していると思います。また刺激量(ショウガ湯の量や灸の熱量)について足りないという考察や指摘があったのですが、この時期被験者は他にもたくさんの鍼灸刺激を受けることを考慮したという研究者の配慮を感じました。またVAS、冷え日記という主観的な指標に対して体温と足表面という局所皮膚温度の2つの客観的指標を計測しています。主観、客観のどちらも2項目計測することが考えられていると思います。
6.非特異性腰痛に対する43℃・46℃の台座灸効果の比較検討 -ペインビジョンの痛み度とVASを指標として―
非特異性腰痛というのは骨折や脊柱管狭窄症のような明確な身体の異常によるものではない腰痛という意味です。いわゆるよく原因は分からないが腰が痛いというもの。レントゲンでも特に異常が見つからないという。一般患者さんにとても多い症例です。その非特異的腰痛がある被験者を対象に台座灸でします。ペインビジョン(胃知覚・痛覚定量分析装置)を用いて「痛み度」を計測します。また痛みの状態を主観的にVASで示してもらいます。そして台座灸は43℃と46℃のもので別々に計測します。台座灸というはメーカの製品で温度が一定に保ちやすくなります。艾を捻る直接灸に比べて温度管理が容易であります。ペインビジョンという装置は被験者が痛みの大きさを電気刺激の大きさと比較することにより「痛み度」として数値化するものです。
まずペインビジョンという知らなかった測定装置。客観的測定(数値化)をどうするのかが全体的な課題です。測定機器が日々発達しており、この卒論発表会ではどんどん紹介される印象があります。私にとっては新しい発見です。43℃というのは既存の研究でTRPV1という体内物質がこの温度以上で活性化するということから、その温度(43℃)とそれより高い温度(46℃)で比較するということです。前の演題同様お灸の実験研究。鍼に比べると扱いが難しいものがあります。鍼は刺してしまえば刺激量は一定ですが、お灸は燃焼させるタイプですと温度が時間によって変わります。どの台座灸も本当に同じピーク温度なのか、温度の変化は一律なのかが懸念になります。灸の実験を選択するのは勇気がいるのではないかと私は思います。昨年発表されたテーマ「施灸による熱刺激が褐色脂肪組織に及ぼす影響 ―刺激温度の高低が褐色脂肪組織の活性化に及ぼす影響について―」では電子温灸器が用いられています。これを受けて研究者は台座灸を選択したのかもしれません。
7.鍼刺激が肩関節角度・筋出力に及ぼす影響 ―刺激量の違いによる検討-
本研究は昨年の「鍼刺激が肩関節角度、筋出力に及ぼす影響 ―刺鍼深度の違いによる検討―」の第二報というものです。棘上筋という肩にある筋肉に対して刺鍼をして肩関節内旋角度と肩関節を外旋させる筋力の変化を測定しています。昨年も刺入深度に違いをつけて2種類の刺激をしています。今年は筋層に達しない刺入の弱刺激群と、筋層に到達しかつ雀啄という刺した鍼を上下に動かして刺激を与える強刺激群、さらに刺鍼をしない無刺激群の3つに分けています。ここでは結果を一部紹介しますが、内旋角度については弱刺激群、強刺激群ともに有意に角度が広がり、コントロール群では変わりませんでした。一方、外旋筋力についてはどの群でも介入後に有意な変化はありませんでした。
筋力を上げる、関節可動域を広げる。これはスポーツに携わる鍼灸師にとって深いテーマになります。私も教員養成科時代の卒業研究では大腿四頭筋に鍼通電刺激を与えて垂直跳びの記録が伸びるかという実験を行いました。臨床では競技ダンス選手をみることが多く施術により筋力が上がる、体が柔らかくなるというのは期待しております。関節可動域については効果があるという報告が多数ありますが筋力が上がったという報告は、自身の実験研究を含めて、聞いたことがありません。吸い玉(カッピング)で握力持続時間が向上したという報告をやはりこの卒業研究発表会で聞いたくらいです。ところがドイツのシステマティックレビューでは鍼刺激により筋力が向上するという報告があるという話を発表で聞き、非常に驚きました。ただ他の報告ではやはり意見がまちまちで鍼により筋力が上がるということは定説ではないようです。ドイツの情報だけでも参加した価値がありました。教員養成科は翌年も研究テーマが継続していくことがよくあります。継続して参加することで分かることがあります。本テーマもその例に当てはまります。
8.経絡治療で頻用される経穴(曲泉・尺沢)への刺激が自律神経活動に及ぼす影響についての検討 ―心拍数及び心拍変動パワースペクトル解析による指標を用いて―
鍼灸には経絡治療というやり方があります。経絡治療の中にも幾つか種類があるのですが。経絡治療では膝にある「曲泉」と肘にある「尺沢」という経穴がよく使用されます。この2ヵ所に鍼刺激をして交感神経活動、副交感神経活動、自律神経活動総量を算出して鍼刺激前後の変化を解析します。鍼は円皮鍼を用いて浅めの刺激を一様に与えるようにしています。置鍼と言ってそのまま7分間そのままにしておきます。扱うテーマは経絡治療という伝統的なもの(現代的な科学重視の鍼灸技法ではないという意味)ですが計測には最新器材を用いています。胸部装着型で着けたまま運動が可能な心拍センサーと指先で測定するものの2種類を使用します。前者が心電図ベースの測定で後者は心電図と静脈波記録のハイブリット型。計測デバイスの比較も行っています。心電図でR―R間隔(RRI)を測定し、そこからソフトウェアでLF(交感神経活動)、HF(副交感神経活動)、TP(自律神経活動総量)を算出します。
本研究の特徴は鍼刺激により被験者の生体にどのような変化があるかを測定するとともに異なる測定デバイスを同時用いて検証していることです。ここで一部結果を書きますが。胸部装着型と指先測定型での測定結果(RRI)は統計処理の結果、ほぼ完全に一致したという結果が出ています。鍼刺激の結果だけでなく測定デバイスが一致した測定を出しているかも実験で確かめているのです。選定した経穴は鍼灸師ならば分かることですが、肝経の合水穴(曲泉)と肺経の合水穴(尺沢)です。
9.「気血水スコア表」の気鬱項目と腹証の心下痞・胸脇苦満の相関について -筋圧痛計を用いて―
昨年の発表テーマ「腹証における心下痞・胸脇苦満と「気血水スコア表」の項目である気鬱との相関について ―筋圧痛計を用いた気鬱の確認―」の続報といえるものです。気血水スコア表とは寺澤捷年によって作られたアンケート質問票です。この回答結果から「気鬱」項目で30点以上と30点未満の2つに被験者を分けて筋圧痛計で腹部を押したときに得られた痛み、不快感の数値(kg)を2群ではいかくします。また被験者個人の気鬱項目の点数と痛み、不快感の数値の相関について調査しています。色々と補足が必要ですが東洋医学には気、血、水の3要素が体調に関係すると考えます。どの要素が原因による不調なのかを質問でみるのが気血水スコアです。各項目があり、気虚、気逆、気鬱、血虚、淤血、水滞の6項目があります。この気鬱項目(100点満点)で30点以上だと気鬱症状があると判断します。被験者を気鬱あり、なしに分けるのです。そして気鬱がある人はお腹に反応が出るとされています。それが専門用語で「心下痞」と「胸脇苦満」です。みぞおち部分(心下痞)と季肋部(胸脇苦満)に圧痛が出る。これは東洋医学特有の腹診手法なのですが、実際どれくらいの強さで押すと痛みや不快感が生じるのか。筋圧痛計を用いて生じたときの重さ(kg)を計測します。
昨年の研究で腹診に客観的な数値を導入したことは慧眼だと書きました。今回は気鬱の有無で違いがあるのかを検証。また痛みの他に不快感という項目を追加しています。筋圧痛計の角度も考慮しています。この研究も昨年の発表を踏まえて改良されていることが分かります。(鍼灸の)腹診は中国よりも日本の方が発達した経緯があります。中国ではかつて鍼灸は皇帝ら身分の高い人物に行うものでお腹を触らせることがなかった。日本では庶民が受けるものとなり、腹部の触診が発達したといいます。また腹黒い、腹の内を見せるなど腹に本心や考えがあるという思想が根付いています。腹診に対する研究があることは注目です。
10.正経12脉の順序について -『霊枢』経脉篇と『書経』洪範編の関係を調べる―
こちらは文献調査の研究です。鍼灸には古典と言われる数百年以上前から存在する文献があります。その研究をすることがあります。脉とは脈の旧字。昔はこの文字を使っていました。現在の東洋医学では全身に12本の経脈があり、それは繋がって循環していると考えられています。しかし最初からそのような記述ではなく時代を経て変化しているのです。それを文献調査し、五行説との関係を考察しています。『霊枢』経脉篇、『書経』洪範編、『足臂十一脈灸経』、『脈書』、『天回医簡』の文献を比較分析し、それぞれが記載する経絡の順序と五行・五臓の関係を比較しています。
この演題が最も分かりませんでした。というのも古典は興味がなくほとんど勉強してきていません。専門学校で習う東洋医学概論でも定説となった理論を学びます。その前段階があったことすら知りませんでした。登場する文献も霊枢しか知りませんでした。報告によると経脈は『足臂十一脈灸経』→『脈書』→『天回医簡』→『霊枢』の順に発展します。最初は経脈は11だったのが『天回医簡』で12に増加。そして一方向に気が流れるとされていたものが『霊枢』経脉篇で循環構造になるというのです。五行説という万物は木・火・土・金・水の5要素に分けられて相互に関係するという理論です。この五行説は『書経』洪範編に最古の記載があり変遷を経て現在の理論になっています。五行も循環します。経脈が循環構造となったのは五行説の影響を受けたのではないか、天体の動きや暦から循環構造に至ったのではないか、学閥争いの結果ではないか、など考察がありました。質疑応答で最も過熱した議論となりました。もはや考古学の分野であり、私にはそうなのかと見守るのみ。ただ今まで興味が湧かなかった古典に初めて面白いかもと感じる発表でした。
11.ハムストリングスに対して押圧刺激を行った際に見られる筋硬度と筋の伸張性の変化
これは数少ない指圧(徒手刺激)における研究です。母校の呉竹学園は鍼灸から始まった学校のせいか、あん摩マッサージ指圧師の研究が非常に少ないです。また鍼灸よりも一般性を保つのが難しいのが徒手刺激。毎回同じ強さで押せますか?という指摘が出ます。本研究は昨年の「あマ指療法における圧刺激変化による筋硬度への影響 ―フェイススケール評価による患者の感受性との関連―」の応用と言えるものです。昨年の研究でも筋硬度計を用いて筋硬度を測定しています。違いとして昨年は筋硬度計で押して押す力を一定にしていたのですが、今回は太ももの下に体重計を置いてハムストリングス(太もも裏の筋肉)を両母指で押して強さを計測します。そして昨年は2.5kg、5.0kgという強さだったのを今回は0kg、1kg、2kgと小さい刺激にしています。ただし1分間の持続圧。各刺激後前後でデジタル筋硬度計により筋硬度を、長座体前屈測定器で伸張性を、測定して変化をみます。
弱い押圧刺激でも効果が出せるのかという問いがあったそう。背景としていわゆるマッサージ行為で健康被害が多数報告されていることを述べていました。技術があればあん摩マッサージ指圧師免許が無くても構わないという世間の風潮に対するものを感じました。ただ指で押すことでも相手の状態によっては大けがに繋がります。そして両母指圧の1分間持続圧法というのはあん摩マッサージ指圧師でないとできないですし、やろうとしないでしょう。基本法として教科書に載ってはいますが。あん摩マッサージ指圧師の研究は今年17演題で唯一。無い年も多数ありました。個人的にとても嬉しいです。
12.頭部への40Hz鍼通電治療による記憶力改善の検証 ―百会穴(GV20)・大椎穴(GV14)への刺鍼-
健常者の被験者に対して頭頂部の「百会」と背中の首の付け根にある「大椎」という経穴に鍼を刺して40Hzの周波数の鍼通電刺激を20分間与えます。その前後にRey-Osteerieth複雑記憶図形検査を行い記憶力の変化を調査します。先行研究でマウス(ねずみ)の実験があります。それを人間に応用しています。またこの手の研究は認知症を患う方を被験者にすることがあるのですが、健常者に行う研究がありません。そこで被験者を健常者に行っています。電気値はテスターで値を計測し0.216±0035mAです。先行研究ではマウスに1.0mAで30分間なので刺激量はかなり下がっています。
術者としては大椎穴に刺鍼をするというのが考えにありませんでした。背骨の棘突起の間です。そこに鍼通電というやり方をする。その手法が新鮮でした。質疑応答でもありましたが記憶力が鍼刺激で向上するとなれば大きな期待です。筋力向上と並んで。過去に例のない研究だと思いました。
13.あはき施術とわいせつ行為について -不同意わいせつ罪を疑われないために―
こちらはアンケート調査を含めた研究です。あはき師とはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の頭文字を取っています。国家資格の分類がこの3つになっています。よってあはき師とはあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師という意味合いになります。あはき師の施術がわいせつ行為として逮捕される報道が不定期に出ています。つい最近にもありました。研究者は事件の調査、法令・裁判例の調査、業界団体・保険会社への問い合わせ、女性へのヒアリングを用いて調査を行います。刑法176条(不同意わいせつ罪)条文、あはき師を含む医療従事者のわいせつ光来が争われた裁判例や過去の事件などの法律関連書籍・資料を調べます。あはき師ではない女性対してGoogleフォームでアンケート調査を実施します。我々の仕事は正当業務行為(違法性阻却事由)というものあたり、本来であればやってはいけない違法行為を、免許を取得することで特別に許されています。医師免許があり医行為として手術だからお腹をメスで切っても傷害罪に問われないように。しかし施術と誤信させたわいせつ行為は違法であるということになります。業界団体ではわいせつ行為と誤信させないためのガイドラインは存在せず、損害補償を扱う保険会社にも保証は対象外であるとのこと。
このテーマは一人で院を開業している私にとって非常に関係する重たいテーマです。抄録を読んで個人的に調査をしました。逮捕例もありますし免許取り消しになったケースも見つかりました。過去の事例やアンケート結果を踏まえると、もう女性患者をみない方が安全ではないかという気にもなります。研究者の言葉にもありましたがわいせつ行為とされるものが時代によって変わったり、個人の受け取り方に差があったりします。当事者としてこれからもずっと向き合わないとならない問題であり、それを再認識させられる発表でした。
14.太白穴・血海穴への円皮鍼刺激が大腿四頭筋の筋力および柔軟性に与える影響 ―遠隔治療と局所治療の比較検討-
大腿四頭筋。人体で最も筋力がある筋肉とされています。「太白」という経穴は足の甲の側面にあります。「血海」は太もも内側(大腿四頭筋上)にある経穴。この大腿四頭筋から離れた「太白」穴と筋上にある「血海」穴に円皮鍼の刺激を与えて大腿四頭筋の筋力と柔軟性を測定しています。東洋医学の特徴とて遠隔治療という概念があります。これは患部から離れた個所を刺激して効かせるという概念。経絡に似た経筋治療という理論があります。これには兪穴・榮穴を用いるというものがあります。先行研究では肝経の兪穴である太白を用いたものがあります。本研究ではこの2つの経穴部分を3つの円皮鍼で囲むように貼ります。そして見た目には区別がつかない鍼がついていないダミーの偽鍼を用いて、太白穴は円皮鍼・血海穴には偽鍼、太白穴には偽鍼・血海穴には円皮鍼、どちらも偽鍼という3群の被験者をつくります。その前後で等尺性膝関節伸展運動により筋力を、踵殿距離で柔軟性を測定します。他の研究にもありましたが筋力と柔軟性が変化するかをみています。
結果はなかなか興味深いというかある種衝撃的なものでした。今後の実験デザインを考える上で重要なものになりそうです。他にも似たような研究報告を知っていますが、この研究結果は知識として知ることができて良かったです。実際に実験したものなので。一方、遠隔治療が実際にできるのかというテーマは鍼灸師として大きな命題です。経絡、気の概念を持ち、気のとおりを良くすることで患部よりも遠いところに刺激をしても効果を出せる。ずっと東洋医学の有利なものとしてありました。このことは今後も考えていかないテーマになります。
15.精油の香りがハムストリングスの伸張性に及ぼす影響
前に説明した通り、ハムストリングスとは太もも裏の筋肉群をさします。アロマの精油。この匂いによりハムストリングスに柔軟性が出るのか。昨年の発表「アロマテラピーがハムストリングスの伸張性に及ぼす影響」の続報という研究です。昨年はラベンダーとローズマリーを用いましたが今年はレモングラスとラベンダーを採用しています。精油の匂いを嗅いだ被験者は1~10(数が大きい方が好き)で嗜好性を回答してもらい、1~6を否定・中立群、7~10を肯定群とします。精油を嗅ぐ前と後で長座体前屈、血圧、心拍数を測定します。
アロマテラピーではレモングラスは興奮作用、ラベンダーは鎮静作用と言われています。気持ちを落ち着かせたかったらラベンダー、気持ちを奮い立たせたいならレモングラスというように。また嗅覚は最も古い感覚といわれています。匂いの影響はバカになりません。私も個人的に精油を用意していて、また新婚旅行では結構お金を出してエジプトの精油を買って帰ったものです。臨床のアクセントに使用することがあり、興味深いテーマでした。
16.円皮鍼が高齢者の非特異的慢性腰痛に及ぼす影響
諸事情により後日の発表となる予定のこと。
17.鍼灸師の施術に対する意識調査 ―患者の受療意識との違い―
背景として鍼灸の受療率は低下傾向にあると報告されています。さらに廃業率は全産業の平均を上回っています。この状況を打破できないかと研究者は患者の潜在的な受療ニーズと顕在的な受療行動に相違があると考えて調査を行いました。調査内容は全日本鍼灸マッサージ師会、日本鍼灸師会に所属する鍼灸師にGoogleアンケートフォームを用いてアンケート調査を行いました。回答者は50代男性が多く、資格取得後平均19.8年でした。
本研究は患者の消費者行動、消費者心理を考えたものになっています。経営戦略やマーケティングの分野に近いでしょう。患者の内面にあるニーズ(潜在的受療ニーズ)に鍼灸師は応えられていないという仮説。実際にベテランと言える鍼灸師の回答を調査して意識のずれがあると考察しています。非常に興味深いアンケート結果でした。私の場合、資格取得後18年、40代後半なのでかなり近い属性になります。ただアンケート結果にはやや違和感を覚えるものがあります。調査対象群が変わると結果は大きく変わるように私は感じました。しかしこのような大規模調査はあまりできていないのが現状であり、貴重な投げかけになります。とても考えさせる発表でした。
今年も教員養成科卒業論文発表会が終わりました。教員養成科の集大成。素晴らしいホールで多くの聴衆の前で正装に身を包み発表します。やり遂げたことが卒業後に大きなプラスになります。今回発表したテーマを次の学年が継いでくれることもあります。微力ながら業界に一石を投じる。今回発表内容でしばし見られたのが「研究の限界」という項目。研究をしてみて時間、器材、人員など様々な限界があり、それを反省点として述べている。それはある種言い訳ですが、未来への期待でもあります。私が教員養成科に在学した11年前には無かった測定機器があります。あるいはあったとしても高価で利用できなかったが、今は安価で手軽に利用できる。今の限界が未来は解消しているかもしれない。
そして今回は会場に鍼灸科、鍼灸マッサージ科の学生もいました。教員養成科卒業生も。進学希望の他校の生徒も。理事長や鍼灸科学科長、大宮校校長など昨年までの代々木校舎では顔を出せなかった教職員も本館で行うため会場に来ました。環境が変わり更なる期待が持てます。来年は学園創立100周年の年になります。これからも楽しみです。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください