開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
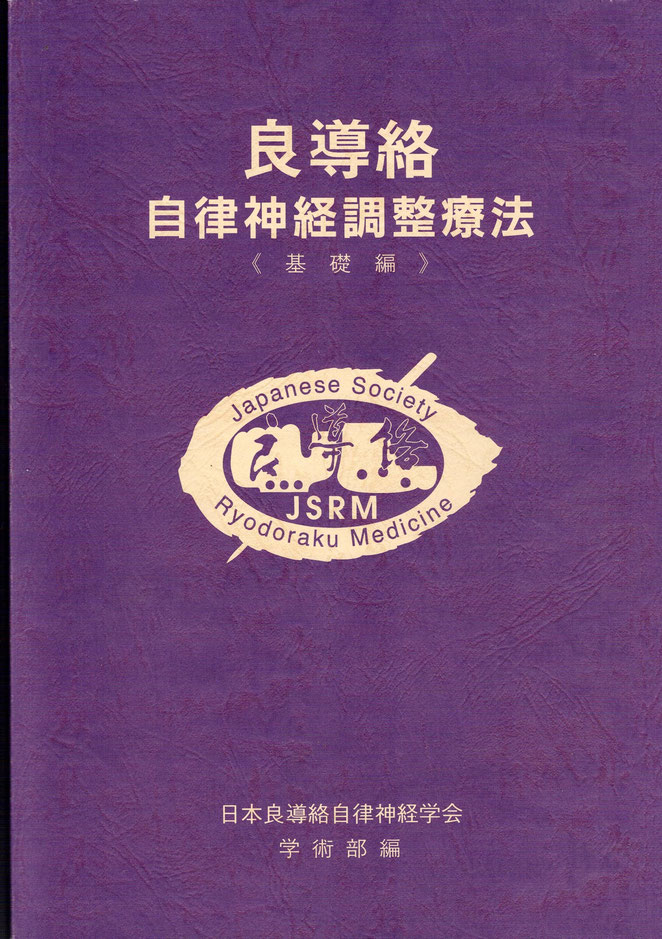
鍼灸の世界には大雑把に3つの流派があります。流派というのは適切な表現ではないかもしれません。ジャンルを分けると3種類になるという感じです。それは現代派、経絡治療、中医学です。
現代派というのは現代科学に即した鍼灸のやり方です。解剖学、生理学を中心に。筋肉、神経、腱などを基準に考える。言うなればあまりいわゆる“東洋医学”(東洋思想)を用いない。経絡とか経穴とか気とかの概念を中心にしないような。医師や他の医療職種にとって分かりやすい。一方東洋医学的な鍼灸としては経絡治療と中医学があります。経絡治療というのも一括りにし過ぎているかもしれないので伝統鍼灸と言い換えていいかもしれません。ただ伝統鍼灸の定義は何か、と言われると困ることになります。『黄帝内経』をはじめとした古典と言われる文献の理論に基づき、経絡・経穴、気血水、陰陽などの理論を踏まえて行う鍼灸。中医学は東洋医学に則しているのですが、近代中国で発展したもの。日本で発展した経絡治療とは理論体系が異なる部分があり、扱う鍼の太さや長さが日本より大きいのが特徴の一つです。ここら辺の話は非常に細かく、当事者には譲れないこだわりがあるところです。
さて現代派の中にも更にやり方があります。その一つに“良導絡”というものがあります。鍼灸というより鍼のやり方です。良導絡とはどのようなものか説明します。
鍼灸師とよく言いますが、日本の国家資格としては「はり師」、「きゅう師」と資格が別々です。同時に養成施設(専門学校や大学)で習いますし、国家試験も同時にするのでほとんどの人は同時に2つ資格をとります。その国家試験には現代医学である病理学や臨床医学各論らの試験と共に東洋医学概論、東洋医学臨床論、経絡経穴概論といった東洋医学分野の科目が必須です。ですから東洋医学を一切学ばずにはり師、きゅう師を取ることはできません。ただ医師免許を持つ者ははり師、きゅう師の免許がなくても鍼灸を業としてすることができます。
良導絡は医師であり医学博士の故中谷義雄氏により京都大学医学部第二生理学教室笹川久吾教授のもとで確立された治療法になります。中谷氏は大阪のデパートで活力測定器を使って増血剤を販売している店員と出会い、その測定器を入手します。それがきっかけとなって良導絡測定器(ノイロメーター)を考案するのです。戦後間もない昭和25年(1950年)にこの測定器を使って腎炎の患者の皮膚の電気抵抗を測定したところ、鍼灸の古典でいう腎経という経絡に似た形の電気の通りやすいスジを発見します。
経絡というのは東洋医学理論でいう気が流れる通路のようなもの。手足から体幹にかけて合計12本の経絡があるとしています。肝・心・脾・肺・腎・心包・胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦の12種類です。肝は解剖学の肝臓と似ているところがありますが一致しているわけではありません。他の臓器にあたる名称も同じです。
中谷氏は東洋医学の知識があったのでしょう。腎経という腎の経絡を知っていました。研究を続け、他にも東洋医学でいう経絡に似た電気の通り易いスジ(経路のような意味)が見つかり、それを“良導絡”と名付けます。現在は良導絡という言葉は技術体系も意味しますが、電気抵抗を測定して電気の通りやすい(伝導しやすい)というところが最初のようです。
中谷氏は実験で良導絡測定器(ノイロメーター)の電圧を21Vに設定して皮膚の通電抵抗を測定したときに、その周辺より電気の通りやすい点が多数出現しました。これを“良導点”と名付けます。さらに電圧を12Vに下げて測定すると、良導点の数は減少するが内臓の異常や痛みなど身体の異常、刺激による交感神経の反射で出現することを発見します。これを“反応良導点”と名付けます。
このように電気抵抗を計測して反応点を特定するという方法を採用しました。現在では簡単なことのように感じるかもしれませんが、計測機器が今よりも乏しかった70年前では画期的だったと思います。良導点の興奮性は、12Vのノイロメーターで測定した時の電流値をもって表します。良導絡上には多くの良導点が存在し、それらの電流値を合計して良導点の数で割ると平均電流が出て、これがその良導絡の興奮性を示します。平均電流に一番近い反応良導点を“代表測定点”と名付け、この電流値により各良導絡の興奮性を現すことにするのです。中谷氏は多数の測定データから基準となるものを割り出します。研究の末、“良導絡測定”という決まったルールの測定方法が確立されます。良導絡測定によって得られた数値を専用の様式でプロットしていくと“良導絡カルテ”となります。
文字にするとどういうものか分からないかと思います。専門的な部分は置いておいて、良導絡の特長を説明していきます。
良導絡はそれまであった古典の経絡の考えを踏襲しています。電気抵抗という物理的な指標を持ちながらも十二経絡と同様に、12の系に分類された病態が体表に現れる「電気の良く流れる特定の部位の連絡の系統」を良導絡としています。経絡には手足に各6つあります。良導絡もH1~H6、F1~F6と定義しています。HはHand、すなわち手。FはFoot、足を意味します。経絡も手の○○経、足の△△経としており、十二経絡とH1~H6、F1~F6の良導絡は対応しております。代表測定点は手首、足首周辺にありますが、これは経絡の原穴といわれる経穴とほぼ一致します。よって東洋医学を学んだ鍼灸師にとって非常に馴染みがあり、反対に東洋医学を知らないとなぜこのようなことになっているのか分かりにくいかもしれません。
良導絡では交感神経の興奮性が電流量と正比例するとしています。各良導絡の電流量(=興奮性)を測定して、良導絡専用カルテに値を記入してゆき平均值、生理的範囲を求めるということをします。そうすることで、各良導絡のデータが標準より高い(興奮)、または低い(抑制)かによって、その良導絡の関係する病態の変化を推定することができるのです。つまり入り口は東洋医学なのですが測定は科学的(物理的)であり、かつ客観的にデータを残すことができるのです。脈診や腹診といった術者の感覚によるものではなく、誰が見てもはっきりする。これが大きいのです。良導絡測定についてはまた詳しく別の機会に触れたいと思います。
測定した結果、どのような刺激をするのか。それが鍼通電です。それも直流電流です。厳密にいうとパルス通電も直流になるのですが、電気を流すことで鍼が腐食する電食という現象を防ぐためにパルス波を流した直後に反対向きに電流を流します。そのため交流のような振る舞いをします。鍼も2本です。良導絡では患者は手に握り導子を握ります。アースの役割です。そして鍼は1本。そこに直流電流を流します。良導絡用の鍼は太く、鍼管という管が長く、鍼体に直接手を触れることがありません。刺激としては、鍼の太さと電流の刺激もあり、強いものになります。その分、パルス通電のように何分も通電するようなことはしません。またパルス通電はパルスジェネレータという装置で出力しますが、良導絡は術者が鍼に電流を流すか否かのマニュアル操作です。
鍼術としては比較的シンプルなのではり師ではない医師も扱いやすいと思われます。基本1本しか鍼を使いませんし。またその成り立ちからも医師よりの鍼灸(厳密には鍼)であり、医師との接点を持ちやすい(医師が理解しやすい)ものだと考えています。また患者さんにとっても良導絡測定でデータが目でみて分かり、施術前後の比較もしやすいというメリットがあります。
良導絡は現代派の鍼として認知されていますが、ベースは経絡経穴の概念です。そこに電気抵抗測定という物理学(科学)的要素が加わった、現代医学と東洋医学の懸け橋になる存在だと考えています。研究もされています。私は良導絡を鍼灸マッサージ教員養成で習いました。臨床では用いませんが大切な技術、理論体系だと思います。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください