開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
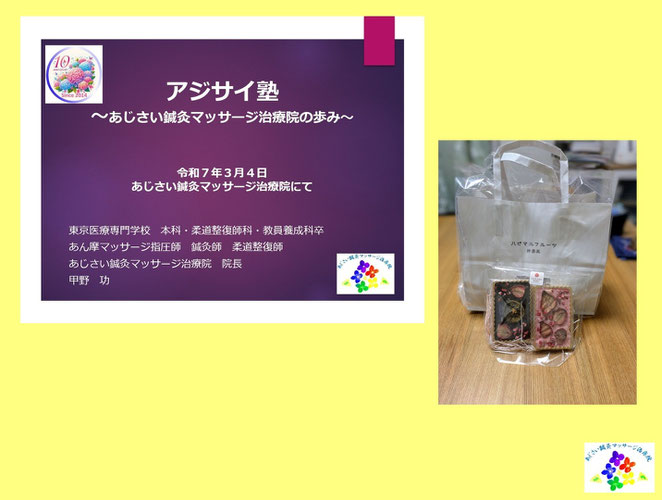
昨日は年内に開業を目指している鍼灸マッサージ師さんの先生が開業へ向けた相談にきました。
その先生は専門学校時代によく当院に勉強に来ていました。現在私が行っているアジサイ塾の最初にあたる人でこの名称を付けたメンバーの一人。当時個人的にある学生さん3名に業界のことや技術知識を不定期で教えていたのですが、仲間内で当院での勉強会をアジサイ塾と読んでいたそう。そのまま私が採用して名称にした経緯があります。昨年女性向け開業座談会を行った鈴木真季先生の同級生で鈴木真季先生に誘われて来るようになっていました。専門学校3年時にコロナ禍が襲い、緊急事態宣言により学校に行けない時期を経験しています。その後無事に国家試験を合格してあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許を取得しました。鍼灸マッサージ専門学校に入る前から別の医療系国家資格を取得しています。そろそろ自分で店舗を持ち独立開業しようと考えているということでした。
事前に先に開業した鈴木真季先生にも相談をしていて場所のこと、コンセプト、ターゲット層など具体的なことを思案しているとのこと。私にはどのような症例が多いのか、患者の年齢層、来院するための経路などを質問したいと連絡がありました。同じ専門学校出身で後輩にあたりますし、かつてよく勉強に来ていた元学生さんです。アジサイ塾延長戦という感じで引き受けることにしました。
そこで困ったことが当院の患者さんデータをまとめていないこと。私は細かく分析するタイプなので、当然患者さん情報も細かく統計を取っていると思われていました。数年前までやろうとして資料を作ったのですが、段々面倒くさくなってきて中断していたのです。患者さんが当院に来た時点での、性別、年齢、住所、属性、主訴、来院経路。これらをもう一度洗い直す必要がありました。これが非常に手間でした。
私は理科系大学を卒業していて、それも物理学専攻で、数学は得意な方です。高校3年間で数学は5段階評価で5しか取ったことがありません。ところが。確率統計は苦手でして、高校数学では一番点数が取れませんでした。大学受験のセンター試験(当時)でも確率統計で大失敗した苦い経験があります。そのため医療統計も学ぶのに苦労しています。今回の依頼でずっと避けていた患者さん属性をまとめることを余儀なくされたというわけです。
結局、私の中では不完全なデータ解析となってしまいました。いつもならもっと手の込んだ資料に仕上げるのですが時間も足りず不完全なものに。それでも日程は待ってくれないので数字を出しただけで資料にせずに(できずに)当日となりました。
それ以外に別の機会に当院の10年を振り返る資料は作成してあったのでそれに手を加えて説明しました。開業前に考えていたコンセプトや狙い、ターゲット層。私の場合、新卒で就職した鍼灸整骨院の段階で独立や経営について考える(悩む)機会がありました。柔道整復専門学校に通いながら職場の経営にも携わっていました。そこから数えると足掛け5年くらいかけて開業のコンセプトを練っていました。特に途中起きた東日本大震災は考えを一変させる出来事でした。この震災でストアコンセプトは大幅に修正されます。余談ですがコロナ禍という世界的影響。このときに周囲では同業者が開業をたくさんしています。大きな社会的衝撃は行動に誘うのかもしれません。
久しぶりに再会した先生。現状を確認します。その上で自分の場合、あじさい鍼灸マッサージ治療院がどうなのかを説明しました。途中約3年間は何度か当院に勉強に来ていたので実感があったと思います。新型コロナウィルスの影響を受けた最初の国家試験受験生となった先生。2021年3月に国家試験お疲れ様会を神楽坂で行い、この1年を様々な点について話し合ったものでした。それから数年。先生が独立開業して自分の場所を持とうと考えた経緯。そして、あじさい鍼灸マッサージ治療院が開院10周年を迎えるまでに何が起きたのか。先生はデータをパソコンでメモしながら聞いていました。
当院の患者さん情報。もちろん個人情報は明かしませんが属性や来院経路などを紹介しました。当然のことですが私の狙い、立地条件などが反映した数字であり、一般的にあてはまるものではありません。私のところの数字は参考にならないという注意はしていました。その前提で男女比、来院経路、自宅からの距離などを聞いていました。先生は何度も当院に公共交通機関を用いて訪れていて、患者さんのメンタリティが実感できるはずです。どうしてうちに来たのか、という点は変わらないでしょう。その上でデータを知ることで様々な考えを巡らせているようでした。当事者である私の考察とは別に。そして自分に置き換えたときにどうなるだろうかと。
開業を考えているエリアやコンセプトも教えてくれました。置かれている状況・環境も。それを踏まえた上で私も意見を述べます。また社会環境の変化、特に先に出された「あはき・柔整広告ガイドライン」が今後及ぼすだろう影響について話をした上で、ホームページ・SNS・紙のチラシらとの向き合い方、作り方などに触れました。私個人の考えとして個人院は術者の個性が具現化したものだと考えています。まず出すのが先生そのものだと。そしてそこで行う(開業する)意味をしっかり持たせて、継続的に発信すること。それが大切ではないかという意見です。
長時間に渡って意見交換となりました。学生時代とは違って独立開業を目指すいち術者として向き合いました。当院の学生サポートという取組を長くやってきた結果です。鈴木真季先生らに続いて開業していただけると嬉しいです。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください