開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
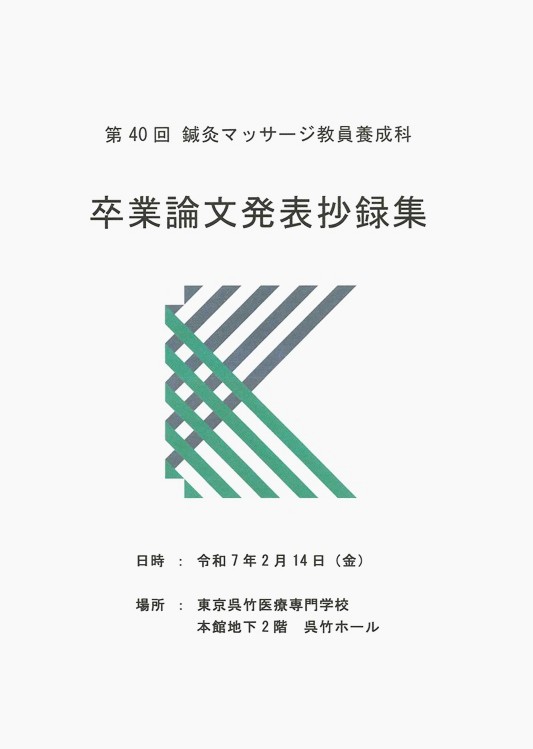
先日は母校の東京呉竹医療専門学校鍼灸マッサージ教員養成科(以下、教員養成科と表記)の学生さんが来院しました。教員養成科は文字通り鍼灸マッサージ専門学校の教員免許が得られる科です。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師免許を取得した者が入学します。母校は2年制です。私も10年以上前に入学し、卒業しております。鍼灸マッサージ学生時代に当院に来た学生さんが教員養成科に入学することはこれまでにありましたが、教員養成科に在籍する鍼灸師さんが当院に来たことは初めてのことでした。
(母校の)教員養成科は卒業要件として卒業研究をしないといけません。それは約1年をかけて行います。毎年2月に卒業論文発表会を行います。いわば学内の学会であり、教員養成科2年生が登壇して研究の成果をプレゼンテーションします。その前に研究テーマ1次報告、2次報告、テーマ決定、研究実施、結果をまとめて考察、抄録作成・提出と様々なポイントがあります。発表準備と並行して論文作成を進め、論文提出までが課題です。卒業論文発表会は会場に教員養成科1年生がおり、先輩の発表を公聴し質疑応答で質問します。発表会が終わると次は自分の番ということで1年後の発表会に向けて卒業研究の準備が始まるのです。
私は教員養成科30期。今年2月に行われた令和6年度第40回卒業論文発表会は41期の発表です。私は教員養成科1年生のときに先輩である29期の発表から同期30期も含めて毎年会場に足を運んで発表を聴いています。今年41期なので13期分の発表を見てきました。今年も質疑応答時間で質問をしました。その際に私のことが気になった1年生の方が声を掛けてきてくださり、今回の来院に繋がりました。
施術を受ける目的もありますが、研究について聞きたいことがあるということでした。卒業論文発表会を体験して次は自分の番だと焦りと不安が生じたようです。どのような研究をしたらいいのか。特に昨年夏に教員養成科は代々木校舎から四谷校舎に引っ越してきて、発表会の会場が新築の本館大ホール(呉竹ホール)になりました。在学中の鍼灸科、鍼灸マッサージ科の学生や本校教職員も会場に入りやすくなり、規模が大きくなりました。研究テーマはどうしたらいいのか、果たして1年後にできるのかという気持ちが芽生えるわけです。
リサーチクエスチョンという言葉があります。教員養成科の卒業研究における指導教員である金子先生がよく用いる言葉です。研究(リサーチ)によってその答えを求めようとしている問い(クエスチョン)というもの。 どのようなリサーチクエスチョンを設定するのか。それが研究の第一歩だといえます。こんな疑問がある。あれはどういうことだろう。素朴な疑問から研究が始まります。一方、社会に役に立たない、倫理的に問題がある、というようなものはリサーチクエスチョンとは言えないでしょう。YouTubeやバラエティー番組の企画と違うのは社会的貢献が見込まれるものがリサーチクエスチョンだと思います。医学論文では“利益相反はございません”と冒頭に注釈を入れることが多いです。これは何かの利益になるために本研究を行ったわけではないと明言しています。医学は社会的責任が大きいため、例えば特定の製薬会社が有利になるように実験を行い、その結果を根拠に薬を売るというような行為をしてはならないのです。研究をはじめるにあたってどのようなリサーチクエスチョンがありますか、という話を来院した方に問いかけました。
リサーチクエスチョンがあったとして、それが研究に落とし込めるのかは次の課題になります。私も経験しましたが、過去に同じ内容の研究があればやる意義が小さくなります。本当にその実験結果は妥当なのか、という科学的批判から追試験という形で行うことはいいでしょう。まだ世にない新たな課題を提示するという意味では既存のものではない研究テーマが必要です。一方、過去に発表された研究結果から条件を変えて行ったらどうなるのか、というリサーチクエスチョンはいいわけです。教員養成科では1年生が2年生の発表を聴いて、私ならこの条件に変えてもう一度研究してみたいと引き継ぐケースが多々あります。年世代もかけて研究されているジャンルもあります。そのことを踏まえてどのようなリサーチクエスチョンを持つのかがポイントです。
大まかなテーマが決まったら先行研究を調査します。実は既に誰かが行っていたテーマかもしれません。また先行研究からより具体的な研究手法が見えてくることはよくあります。言い換えるとリサーチクエスチョンに関連した先行研究を調査してテーマが定まるという。私の場合は臨床で起きた一つの成功体験を、あれはたまたまだったのか普遍性があるものなのか、というリサーチクエスチョンから卒業研究が始まりました。関係する先行研究を調査して実験手法が決まっていきました。
私の経験談。過去の発表例。それらの情報を提示しながら相談に乗りました。時間、設備、人(被験者、実験者を含めて)、資金、機材などリソース(資源)は限度があります。研究が実現可能かも踏まえて実験プロトコルを決定しないといけません。文献調査やリサーチ研究でもリソースには限度があります(この場合は主に時間)。おそらく具体的な行動に移すと想定通りには物事が運ばずに軌道修正を余儀なくされることが多いでしょう。その兼ね合いも考えて研究を成し遂げないといけないわけです。まだ始まったばかりで具体的なことは考えられていないようでしたが参考になると話を聞いていました。
私は学会発表レベルの研究は教員養成科以来してはいないのですが、日々リサーチクエスチョンは浮かんで確かめることはしています。こうしたらどうなるだろうか。これはいったいどういうことなのだろうか。好奇心に近いかもしれません。そのことを再発見しました。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください